
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、理学療法士の離職率と継続率ついて考えていきたいと思います。

全体の動向は気になりますね。

現状の実態を把握し、自院でのリクルートや教育環境の再考に役立てましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
理学療法士として働いていて、「この仕事を続けていけるだろうか」「将来に不安を感じる」と思ったことはありませんか?
実は、多くの理学療法士がキャリアの途中で悩み、離職を選ぶケースも少なくありません。
本記事では、最新の統計データをもとに、理学療法士の継続率や離職率の実態、そして今後継続して働くためにできることを徹底解説します。
理学療法士の継続率とは?現状と基本データの把握
理学療法士はリハビリ医療の現場で欠かせない存在ですが、その「継続率」や「離職率」はあまり知られていません。継続率とは、理学療法士が資格取得後に現場で働き続けている割合を指します。
2023年の厚生労働省の雇用動向調査によると、医療分野における理学療法士の離職率は約10.2%、介護福祉分野では約18.8%と報告されています。これは、産業全体の平均離職率15.0%と比較して、勤務先によって大きな差があることを示しています。
また、卒業後3年以内に離職する理学療法士も少なくなく、「3年で約3割が離職する」というデータもあります。この現状を理解することが、継続率向上の第一歩です。
理学療法士の継続率が下がる主な要因とは?
理学療法士の継続率が課題となる背景には、いくつかの共通する要因があります。
第一に、職場環境の問題です。特に人間関係や長時間労働、休日取得の困難さなどが、離職の大きな原因となっています。患者との関係性はやりがいの源ですが、それを支える組織環境が整っていなければ、継続は困難です。
第二に、キャリアパスの不透明さです。理学療法士として成長していく明確な道筋が見えづらいことが、中堅層のモチベーション低下に繋がっています。
さらに、卒後教育の不足や、エビデンスに基づいた実践(EBP)の低実行率も問題です。ある研究によると、理学療法士のEBP使用率は、卒後3年以内に64%も減少すると言われています。
継続率を高めるためにできること・今後の展望
理学療法士の継続率を高めるためには、組織と個人の両方からのアプローチが不可欠です。
まず、組織としての取り組みとして注目されているのが、日本理学療法士協会による新しい生涯学習制度です。この制度では、キャリア段階に応じた研修を受けられる仕組みが整備され、理学療法士としての専門性を高める支援が進んでいます。
個人レベルでは、キャリアデザインの明確化とスキルアップがカギです。自身の専門性や興味に合わせて学び直しを行うことで、将来に対する不安を軽減できます。近年では、オンライン研修や学会発表の支援など、学びの選択肢も増えています。
将来的には、EBPの実践率向上や、多職種連携の強化によるやりがい向上なども継続率の改善に貢献すると考えられます。
まとめ
理学療法士の継続率は、職場環境・キャリア設計・教育制度など、複数の要素に影響を受けています。
特に、勤務先によって離職率に差がある現実は、働き方の再考を促すものです。
長く安心して働くには、職場側のサポート体制と、個人の学びや挑戦への姿勢が両輪で必要です。
理学療法士として充実したキャリアを築くために、今できることから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか?
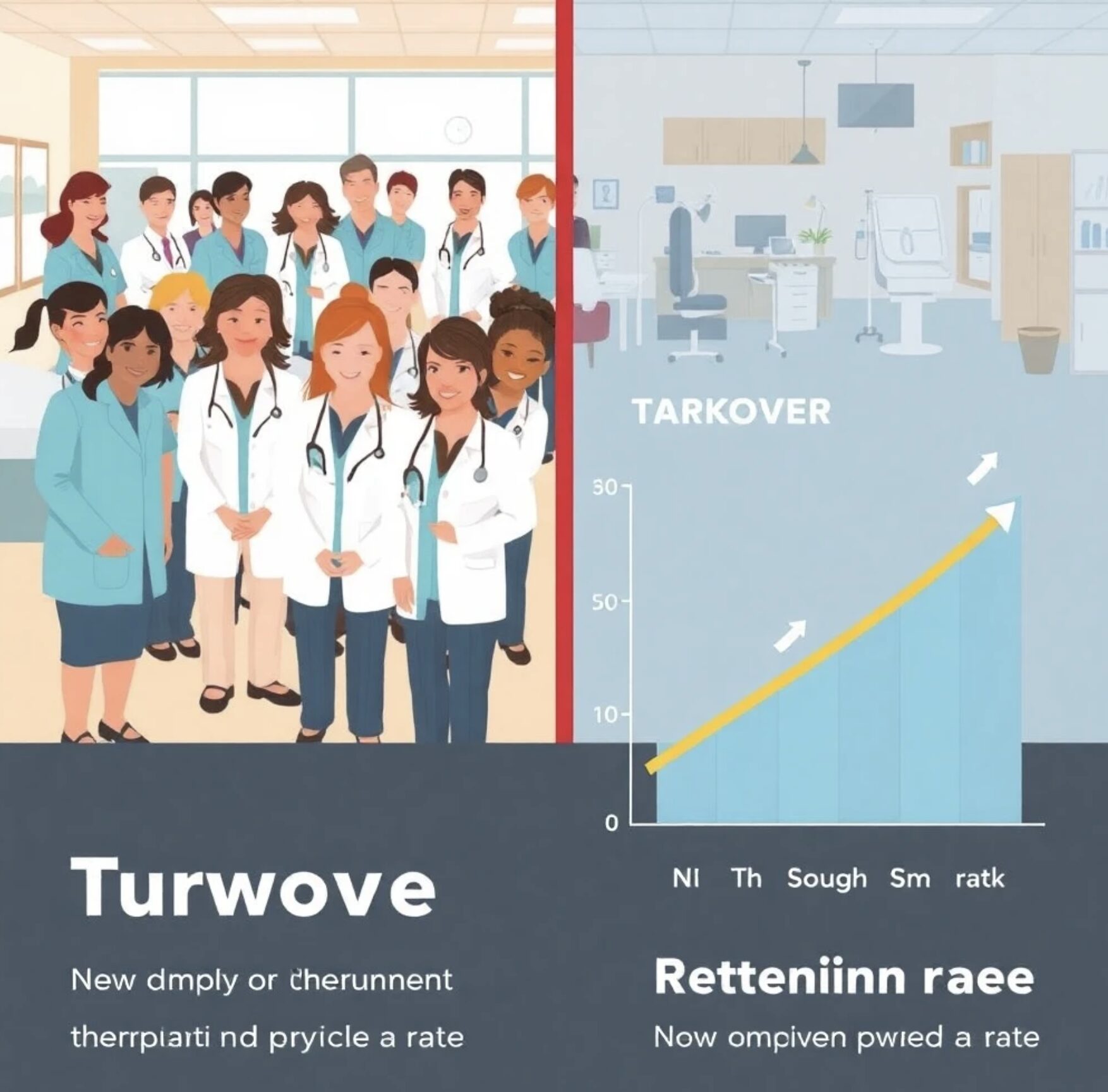


コメント