
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、権威について考えたいと思います。

パワー??・・・

今回は、権威よりも導くことについて考えてみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
「昔はこうだった」「自分の頃はもっと厳しかった」。そんなセリフに心当たりはありませんか?
リハビリ現場において、経験豊富な管理職の存在は大きな支えです。しかしその経験が、時に“老害”と揶揄される要因になることも。特に若手スタッフとの価値観のズレや、一方的な指導スタイルは、信頼関係を損ないやすく、離職の原因にもつながります。
この記事では、権威に頼らず、共感とコーチングを重視することで「老害指摘」から脱却し、信頼される管理職になるためのポイントを、科学的根拠と実例を交えながら紹介します。
なぜ“老害”と見なされてしまうのか?現代の管理職に求められる役割
時代の変化と“上から目線”の終焉
昭和・平成のマネジメントと令和のマネジメントでは決定的な違いがあります。昔は「指示命令型」のリーダー像が主流でしたが、現代の若手世代は「対話・共感・納得」を重視します。
厚生労働省の「働き方改革実行計画」においても、心理的安全性の高い職場づくりや、対話型リーダーシップの重要性が強調されています。
老害とされる特徴(引用:若手職員アンケート調査より)
- 自分の成功体験を押し付ける
- 部下の意見を遮り、結論を決めつける
- 若手の提案に対して、「そんなことは昔からやっている」と否定的
- 情報ツールやICTを拒絶し、紙ベースでの管理に固執
こうした言動が、部下の心理的安全性を低下させ、管理職自身の信頼を失う原因となります。
共感とコーチングが信頼を生む理由
“指示”より“問いかけ”が部下を育てる
カリフォルニア大学のコーチング研究(2018)では、「共感を伴う質問」により自己効力感が向上し、部下の学習意欲や定着率が高まることが明らかになっています。
具体的な問いかけ例:
- 「どうすればもっと患者さんとの関わりが良くなりそう?」
- 「このケースについて、あなたならどう考える?」
これらは、「指示」ではなく「内省と提案の機会」を与える問いです。
コーチ型リーダーとは
リハビリ管理職に求められるのは、以下のような資質です:
- 共感力と傾聴力
- 批判よりもフィードバック重視の姿勢
- 成長を支援するマインドセット
現場での「支配」よりも、「成長の伴走者」になることが、若手との信頼関係構築に不可欠です。
リハビリ現場で実践する“脱・老害”マネジメント
具体的な取り組み事例
事例1:ICT活用を推進する管理職A氏
電子カルテやリハビリ記録アプリの導入を若手に任せ、年配スタッフにも研修機会を設けることで、組織内の情報格差を縮小。
事例2:月1回の1on1面談導入
フィードバックとキャリア相談を定期的に行うことで、離職率が20%低下(導入前比較)。
事例3:失敗を責めない文化づくり
ヒヤリ・ハット事例を共有する「安全ラウンド」を導入し、自由な意見交換を促進。
経験は“価値ある資産”として活かす
ベテラン管理職の経験は、組織にとって財産です。ただし、それを「正しさの証明」ではなく、「選択肢の一つ」として語ることが重要です。経験を活かしつつも、部下に選ばせる姿勢が、共感と信頼につながります。
まとめ:共感とコーチングで、“頼れるベテラン”に変わる
「老害」とは年齢の問題ではなく、マネジメントの姿勢の問題です。
管理職が権威に頼らず、共感力とコーチングスキルを磨くことで、若手との信頼関係を築き、組織全体の活性化につながります。
🟩本記事のポイント:
- “老害”とされる特徴を自覚することが第一歩
- コーチングマインドの導入が若手の離職を防ぐ
- 経験を「支配」ではなく「支援」に活かす
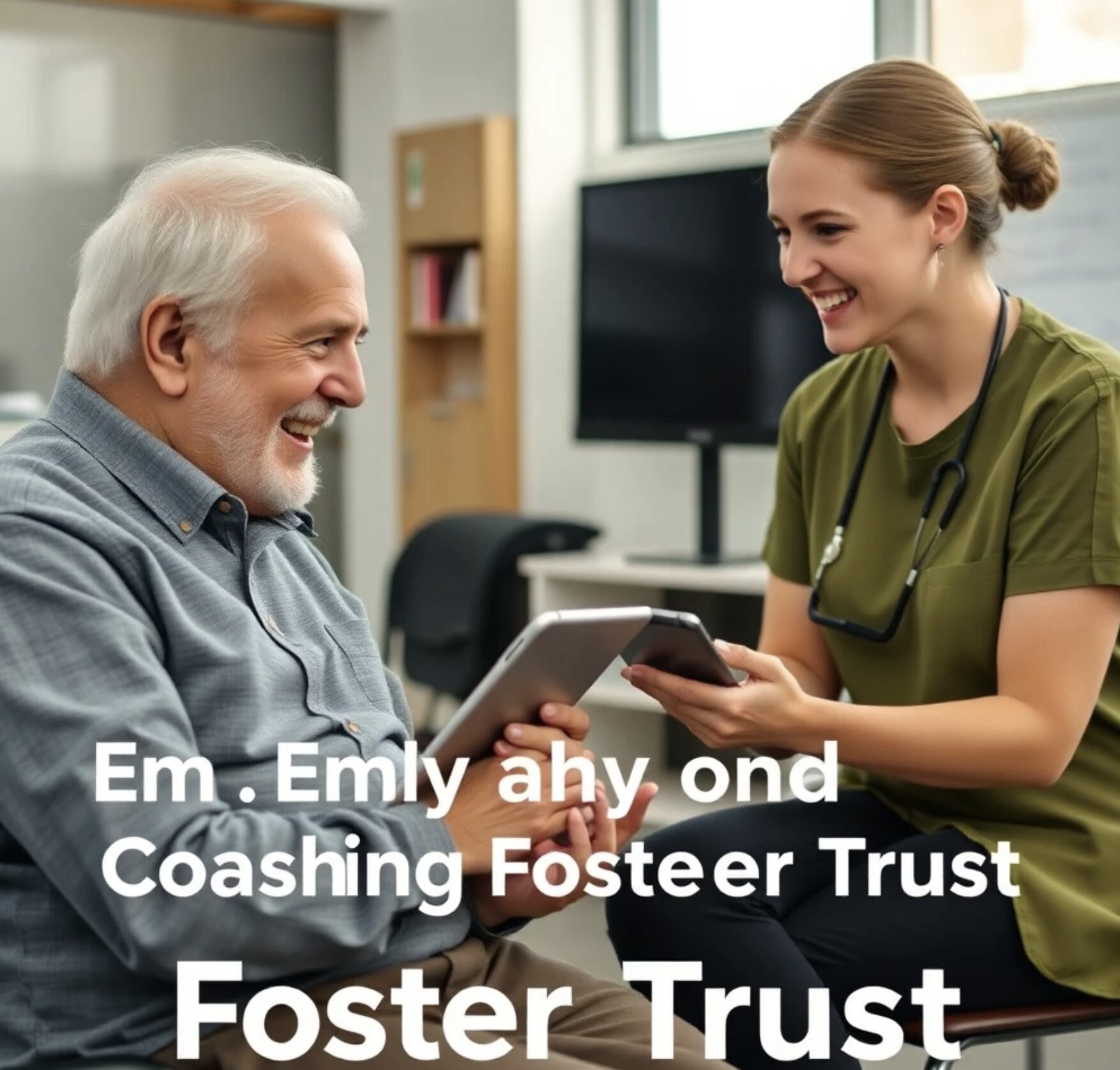


コメント