
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、仕事ができる管理職について考えたいと思います。

スタッフ側にどう見られているか・・・

今回は、胸を張って管理職として仕事をしましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
「リハビリ現場で“仕事ができる”と思われている上司って、どんな人ですか?」
その答えは、技術や知識の多さだけではありません。実は、部下が安心して任せられる、信頼できる行動が鍵なのです。
本記事では、リハビリ管理職が「この人は仕事ができる」と部下に感じてもらえる行動と、その仕組み化の方法について、心理学とマネジメント理論の視点から解説します。
なぜ「できる管理職」と思われることが重要なのか?
リハビリ現場における管理職は、単なる監督者ではなく「信頼されるリーダー」である必要があります。
ハーバード・ビジネス・レビューによると、チームの心理的安全性はリーダーに対する「信頼」と強い相関があるとされ、信頼が高まるほど報告や相談、アイデアの共有が促進されることが示されています。
つまり、「この人は仕事ができる」と思われることは、信頼の基盤を築くことに直結します。
その信頼が、結果としてスタッフのモチベーションや協働姿勢に大きく影響し、現場の質にも反映されるのです。
部下が感じる「できる上司」の行動とは?
では、部下はどんな行動を見て「この人は仕事ができる」と感じるのでしょうか?
以下のような特徴が心理学的にも効果的とされています。
- ロジカルで一貫した指示:曖昧さを排除し、目的→手段→期待する成果を明確に。
- 話を最後まで聞く姿勢と具体的なフィードバック:部下は“聞いてもらえる安心感”で能力を発揮します。
- 感情のコントロール:特に緊急対応時、冷静に判断し落ち着いた言動が信頼を生みます。
- 適切な権限移譲とフォローアップ:任せっぱなしにせず、結果を振り返る“確認の習慣”が評価されます。
再現性のある行動を習慣化する仕組み
「できる上司」と思われるには、意識的に行動を“設計”する必要があります。以下のような具体的施策が有効です。
- 1on1・カンファレンスの質向上:目的設定シートやトピックテンプレートを事前共有
- 行動記録・チェックリストの活用:伝えた内容やフィードバックを「見える化」する
- フィードバック文化の育成:定期的な振り返りMTGやピアレビューを制度化する
これにより、属人的ではない「仕組みとしての信頼構築」が可能になります。
まとめ:部下の視点から逆算して行動を設計しよう
「この人についていきたい」と思われる管理職には、共通点があります。
それは「一貫性」「聴く姿勢」「冷静な判断」「仕組みに基づく信頼」の4点です。
日々の業務に追われる中でも、仕組みによって行動を習慣化し、再現性を持たせることが“できる上司”への近道です。
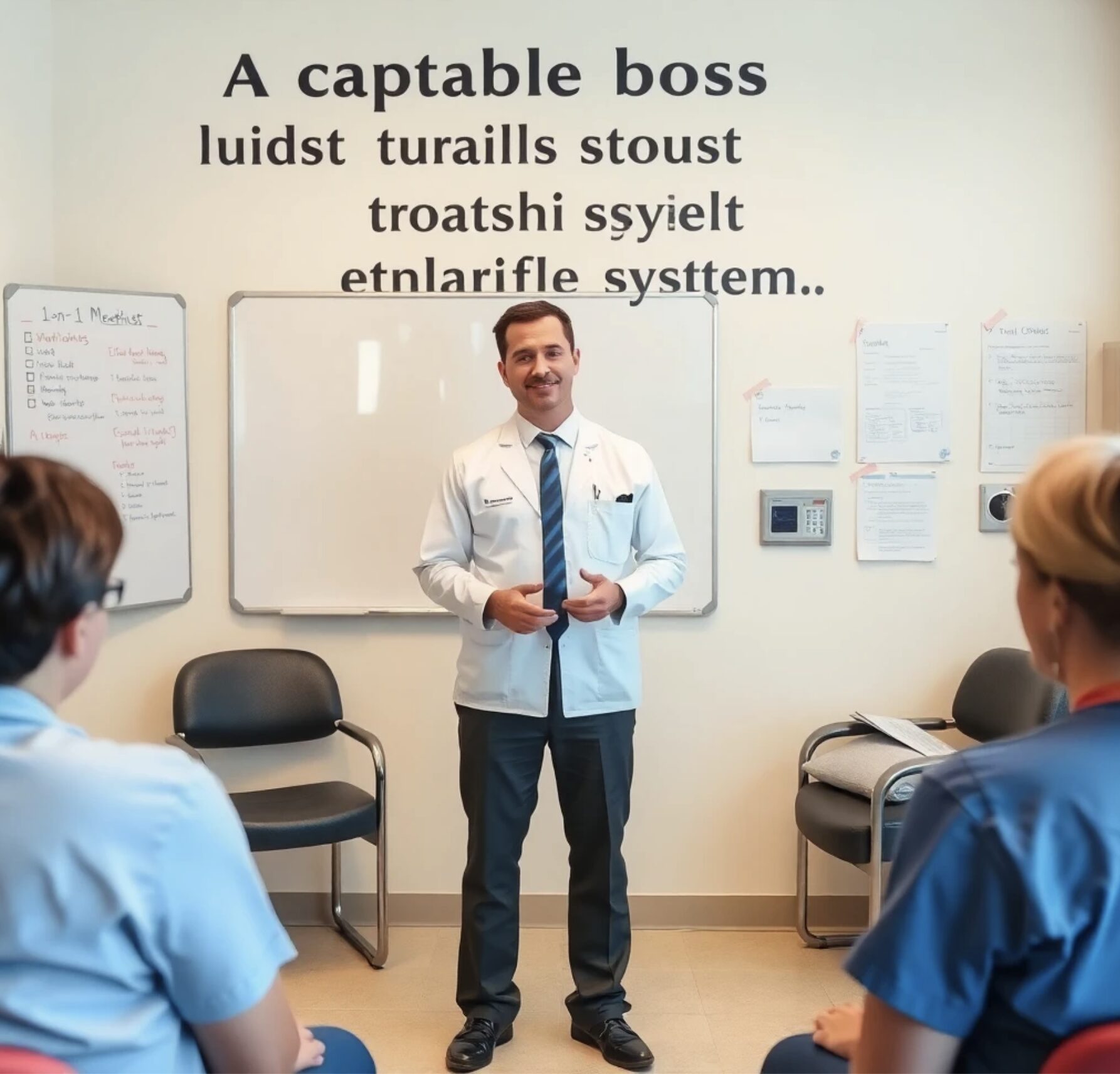


コメント