
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、間接業務について考えましょう。

持ち帰ることはあまりないかな・・・

業務を効率的に回す仕組みづくりについて考えてみましょう。
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
リハビリ現場で働く管理職やスタッフにとって、記録や事務を家に持ち帰ることは「当たり前」のように続いてきました。しかし、その負担は働き方だけでなく、患者安全や職場の活力にも影響を与えます。本記事では、持ち帰り残業をなくし、業務を効率的に回す仕組みづくりについて解説します。
なぜリハビリ職は記録と事務を持ち帰ってしまうのか?
リハビリ職の1日は、患者対応だけでは終わりません。評価票や計画書、報告書など、**「見えない事務作業」**が常に付きまといます。
急性期病院では病棟回転率を意識した業務、回復期病院では多職種カンファレンス、地域包括ではサービス調整など、記録時間を確保しづらい状況が当たり前です。その結果、**業務時間外に記録を持ち帰る“隠れ残業”**が発生します。
しかし研究によれば、長時間労働と疲労の蓄積は判断力の低下や医療事故リスク増加と関連していることが報告されています(厚労省, 2020)。
つまり、「持ち帰り作業」は個人の問題ではなく、組織全体の安全管理の課題でもあるのです。
事務負担を減らすための“仕組み”づくり
「根性で乗り切る」ではなく、仕組みで解決することが重要です。
- ICT導入:電子カルテ、音声入力アプリ、クラウドベースの進捗管理で記録時間を短縮
- 標準化フォーマット:誰でも同じ手順で入力できる評価票・計画書を整備
- タスク分担:事務作業をアシスタントや事務スタッフとシェアし、専門職の業務集中を促す
実際の研究でも、医療現場にICTを導入すると記録業務が30〜40%削減できると報告されています(BMJ Open, 2019)。
つまり、効率化は「ツール×仕組み×役割分担」の組み合わせで実現可能です。
今日から始められる実践的アプローチ
「仕組みを作るのは時間がかかる」と思うかもしれません。ですが、今日からできる小さな工夫もあります。
- 即時入力習慣:評価後すぐにカルテへ入力するルール化
- 会議短縮&クラウド共有:話し合いは要点だけ、その後の共有はクラウドに集約
- 管理職の姿勢:まずは管理職自身が「持ち帰らない」を実践し、モデルを示す
研究では、タイムマネジメント教育を受けた医療職は業務効率が改善し、ストレスが軽減する効果があると示されています(JAMA, 2021)。
小さな一歩の積み重ねが、やがて「持ち帰らない文化」をつくるのです。
まとめ
リハビリ現場の「持ち帰り事務」は、根性や努力で解決するものではありません。
- ICTや標準化で記録時間を削減する
- チームでの役割分担で負担をシェアする
- 即時入力や会議短縮といった小さな習慣を積み重ねる
これらを実践すれば、「持ち帰らない」働き方が現実になります。
管理職が率先して取り組むことで、職場全体の負担軽減と安全性向上が同時に実現できるのです。
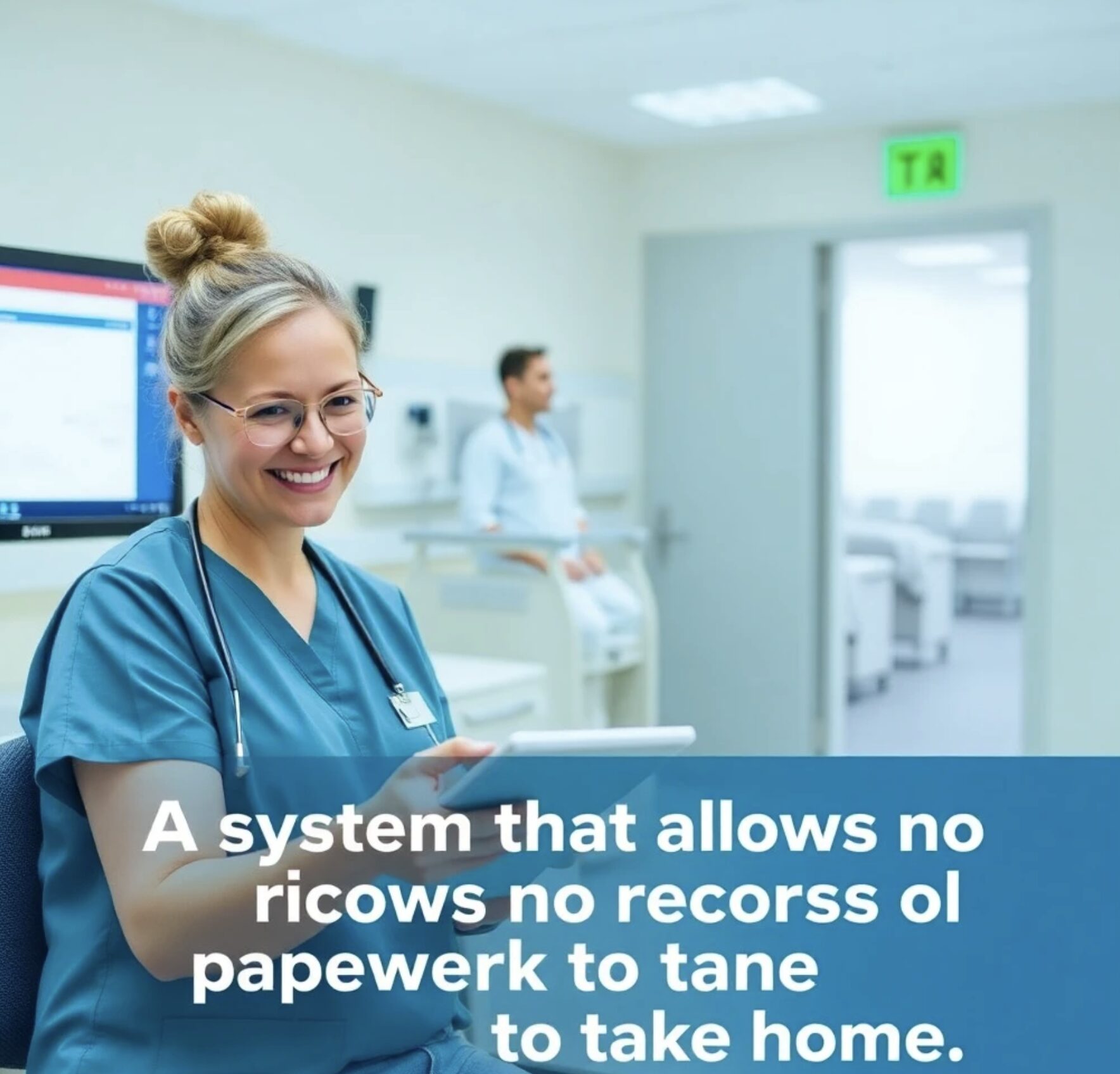


コメント