
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、忙しい時の学びのテクニックについて考えましょう。

んー?・・・

研修に行けない時代でも専門性を維持することについて考えてみましょう。
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
リハビリ現場の管理職にとって、「研修に行けない」ことはもはや特別ではなく日常となりつつあります。しかし学びを止めることは、現場の停滞や部下育成の遅れにつながります。本記事では、研修に行けない時代でも専門性を維持する“学びの分散化”テクニックを紹介します。
なぜ今、リハビリ管理職は研修に行けないのか?
リハビリ現場の管理職にとって、学会や研修会はかつて専門性を磨く大切な場でした。しかし近年は、人手不足・業務量増加・感染症リスクなどの要因で「行きたくても行けない」状況が続いています。
研修に参加できないことで、最新の治療技術やガイドラインを知らないまま現場を率いるリスクが生じます。さらに、教育を受けられないスタッフに「管理職がアップデートしていない」と思われると、信頼関係にも影響しかねません。
実際、国内の医療人材研究でも「継続教育へのアクセス不足は専門性維持に負の影響を与える」と報告されています(日本リハビリテーション医学会, 2022)。
学びの分散化とは?リハビリ管理職に必要な視点
「研修に行けない=学べない」ではありません。現代では**学びの分散化(Learning Decentralization)**が重要です。
分散化とは、学会や集合研修に依存せず、オンライン教育・現場での経験・他職種交流といった複数の学習経路を組み合わせる考え方です。
- オンライン学習:PubMedのオープンアクセス論文やYouTube学会チャンネルで最新知識を得る
- 現場学習:カンファレンスでの議論を“実地研修”として位置づける
- 相互学習:部下や若手の意見をフィードバック源にする
成人学習理論によると、大人の学びは「自律性・経験・即時性」が鍵です(Knowles, 1984)。つまり、管理職は「日々の現場と結びついた学び」を積極的に設計する必要があります。
すぐに始められる実践例と仕組み化のヒント
理論を知っても「どうやるか」がなければ意味がありません。ここではすぐ実践できる分散型学習の工夫を紹介します。
- 1日15分の文献レビュー習慣:朝の隙間時間に1本論文を読む
- 病棟カンファを教育の場に:最新ガイドラインを引用しながら議論する
- AI活用:ChatGPTなどで論文の要約や知識整理を効率化
- マイクロ研修:学んだことを5分だけスタッフに共有する
これにより、研修に行けなくても「常に学び続けている管理職」であることを周囲に示すことができます。実際、欧州の医療教育研究でも「学習の小分割化と共有が専門職の知識定着を高める」と示されています(Boud & Hager, 2012)。
まとめ
研修に参加できない時代でも、学びを止める必要はありません。
- オンライン・現場・相互交流を活用する「学びの分散化」
- 成人学習理論に基づいた、即効性のある学習設計
- 日常業務に学びを組み込み、スタッフに還元する仕組み
これらを取り入れることで、研修ゼロでも専門性を維持し続ける管理職へと進化できます。
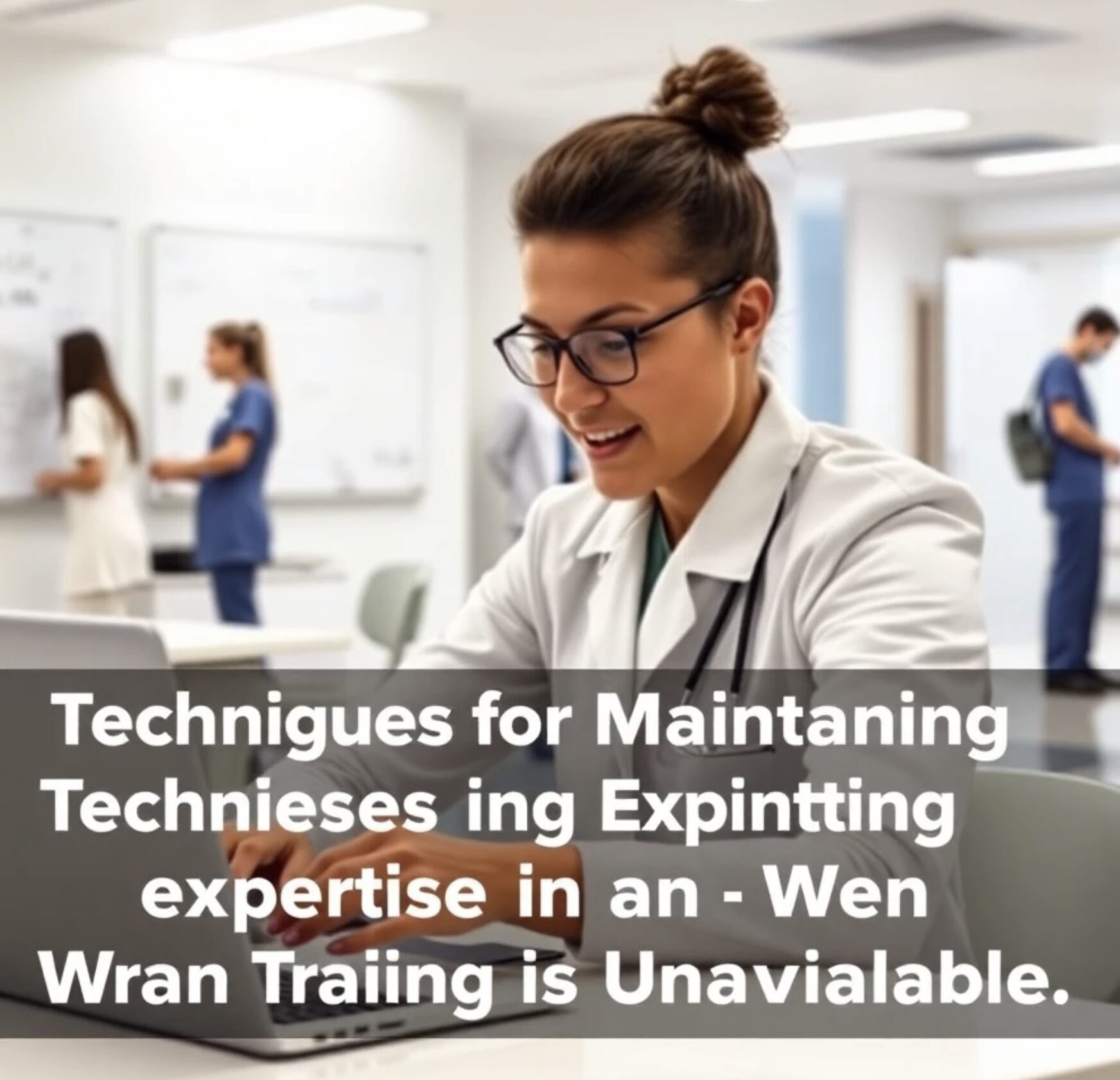


コメント