
もんきち
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、越境学習について考えたいと思います。

スタッフ
越境学習?

もんきち
今回は、組織の壁をを越える越境学習について考えてみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
「多職種連携って言うけれど、実際は壁ばかり…」
そう感じるリハビリ管理職の方は多いのではないでしょうか。
専門職としての経験は豊富でも、他部署・他職種との関係構築はまるで別のスキル。
そのとき頼りになるのが、「越境学習」という考え方です。
本記事では、越境学習の理論と、実際の事例を紹介しながら、
明日から実践できるリハビリ管理職の越境戦略をお届けします。
越境学習とは何か?
リハビリ現場において、PT・OT・ST・看護師・医師・MSWとの連携は避けて通れません。
このとき生まれるのが「境界」。専門性、価値観、言語の違いによって、協働が難しくなる瞬間です。
そこで注目されているのが、**越境学習(Boundary Crossing Learning)**という概念です。
Akkerman & Bakker(2011)は、越境学習を以下の4つに分類しました。
- 識別(Identification):違いに気づく
- 調整(Coordination):互いの作業をつなぐ
- 反省(Reflection):他者視点から自らを見直す
- 変換(Transformation):新たな実践を共創する
越境学習は、ただ“他部署と関わる”だけではなく、学び合い、意味を再構築する対話的プロセスです。
リハビリ管理職における越境学習の実例
◉ 事例:回復期リハ病棟の管理者Mさん
MさんはPT出身の管理職。看護師との連携に悩み、情報共有がうまく進まない日々。
彼は以下のような“越境体験”を通して、チームを変えていきました。
- 他職種カンファレンスに参加(識別〜調整)
- 看護記録にある「自立度」や「離床支援」の観点が、リハビリと異なると気づく。
- 看護師とのラウンド同行(反省)
- 「移乗動作」だけでなく、「トイレ介助のタイミング」に注目すべきと認識。
- 新しい共有シートを開発(変換)
- 「生活支援観点でのゴール設定」をリハと看護で統合する仕組みを導入。
結果、多職種連携の信頼度が向上し、患者満足度アンケートも向上。
これはまさに「変換」まで進んだ越境学習の好事例といえます。
明日からできる!越境学習の3ステップ
越境学習を実践するには、ちょっとした“仕掛け”が必要です。以下の3ステップを試してみてください。
① 境界を「見える化」する
- カルテ記録の言葉の違いを比較してみる
- 多職種ごとの業務フローを図解化する
② 学びの場を“交差点化”する
- あえて「目的が異なる」職種と合同勉強会を開催
- 日常の振り返りミーティングに「他者視点での感想」を入れる
③ 小さく変換してみる
- 既存の業務ツール(例:目標設定シート)に、他職種の欄を追加
- 「担当者不在でも伝わる伝達手段」を考案する
まとめ
- 越境学習は「他者の視点で自分を見る」機会をつくる営み
- リハビリ管理職は“境界”に立ちやすい立場であり、越境のチャンスが豊富
- 見える化 → 交差点化 → 小さな変換 という3ステップで、実践は可能
今後、医療現場のチーム力は、「境界を越えられるリーダー」にかかっています。
ぜひ、自身の現場でも越境の第一歩を踏み出してみてください。
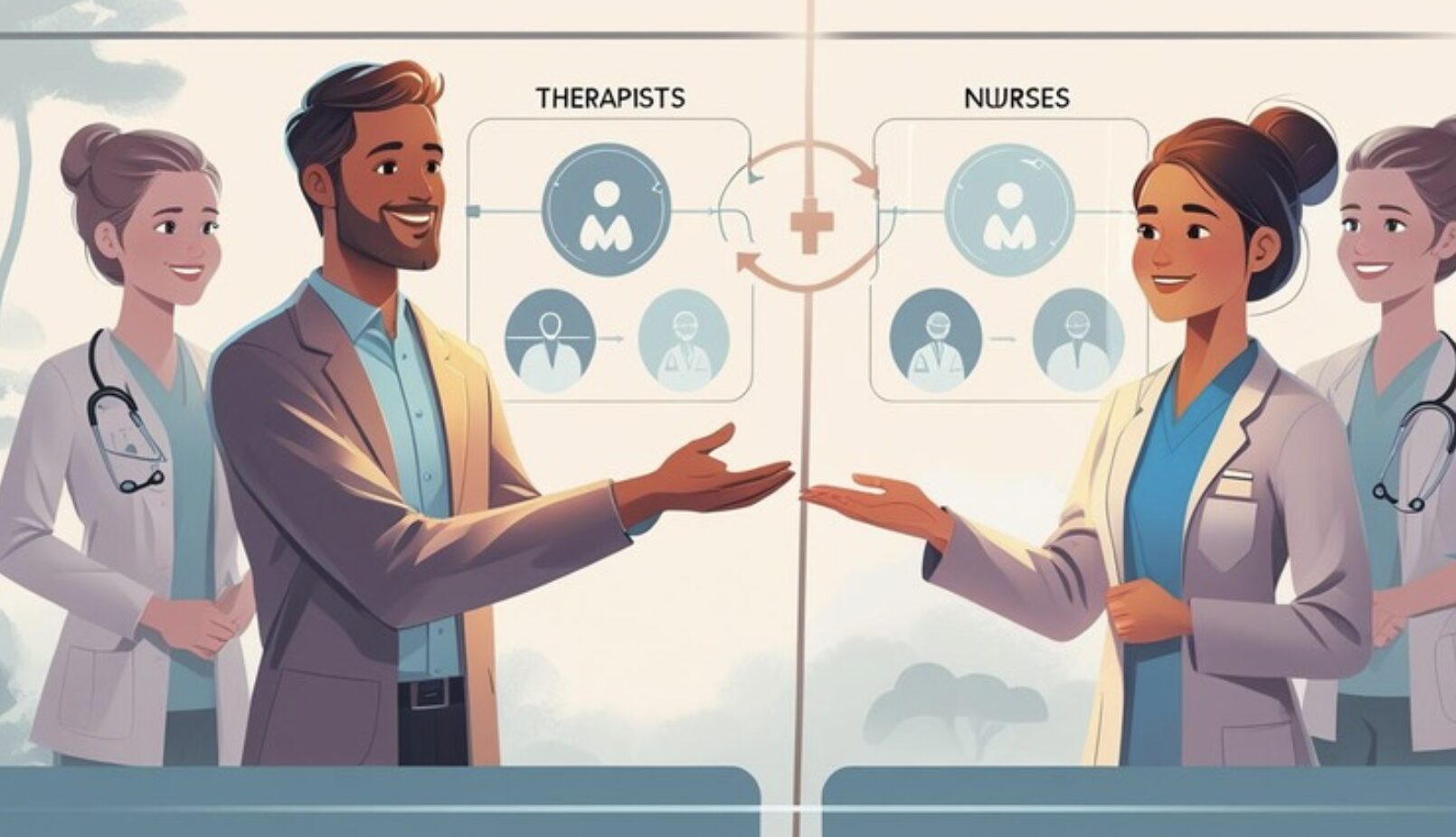


コメント