
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、育児・介護・昇進の「三重課題」について考えましょう。

あるあるですね・・・

先を見通したライフキャリアマップの作成について考えてみましょう。
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
リハビリの管理職は、育児・介護・昇進の「三重課題」に直面しがちです。5年後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、先を見通したライフキャリアマップの作成が欠かせません。本記事では、学術的な根拠をもとに、家庭と仕事をつなぐキャリアマップ術を紹介します。
なぜリハビリ管理職に「ライフキャリアマップ」が必要か?
リハビリ現場の管理職は、臨床・教育・マネジメントの3役を同時にこなすことが求められます。加えて、自身の家庭では「育児」や「介護」といった大きなライフイベントが重なりやすい時期。昇進や責任の増大と重なれば、まさに「トリレンマ=三重の板挟み」に直面します。
キャリア理論の巨匠Superは「人は複数の役割を同時に生きる」と述べています(ライフスパン・ライフスペース理論)。つまり、職場だけでなく家庭や地域での役割もキャリアに含まれるのです。さらに、Work–Family Balance研究でも「仕事と家庭のバランスを取る人は、バーンアウトが減り、生産性も高い」ことが示されています。
だからこそ、管理職リハビリセラピストには「将来を見通したキャリアマップ」が必須となるのです。
ブロック2:5年後を見据えたキャリアマップの作成ステップ
後悔しない未来をつくるには、漠然と「頑張る」だけでは足りません。具体的に、次の3ステップでキャリアマップを描くことが有効です。
- 家庭イベントを予測する
育児なら入学・進学、介護なら要支援から要介護への変化など、ライフステージの節目をリスト化します。 - 職場のキャリアを整理する
昇進のタイミングや役職の可能性、プロジェクトの節目などを想定します。 - タイムラインで重ね合わせる
家庭と職場の両方を年表に落とし込み、重なりが大きい時期を「要注意ゾーン」として可視化します。
心理学のFuture Time Perspective理論では「将来を明確に意識できる人ほど、柔軟に準備しやすい」とされています。つまり、キャリアマップは未来を“見える化”するツールなのです。
ブロック3:キャリアマップを実行に移す「週次ミニレビュー」
キャリアマップは作って終わりではなく、小さな修正を積み重ねることで効果が高まります。具体的には、週1回10分の「ミニレビュー」をおすすめします。
- 家族と予定を確認し合う → 急な行事や介護負担の変化を早めに把握
- 職場では、上司や同僚と情報を共有 → 無理のない役割分担を調整
- 自分の気持ちを整理 → 「今は踏ん張る時期」か「調整すべき時期」かを見極める
自己決定理論(Deci & Ryan)によれば、人は「自律性・関係性・有能感」が満たされるとストレスに強くなります。週次レビューはまさに、この3要素を育てるセルフマネジメントの習慣なのです。
まとめ
- リハビリ管理職には、仕事・家庭・昇進のトリレンマがある
- キャリアマップは「家庭イベント×職場キャリア」を重ね合わせて作成する
- 成功の鍵は「週次ミニレビュー」での継続的な調整
未来を描き、柔軟に修正していくことで、5年後の自分に後悔しないキャリアを築くことができます。
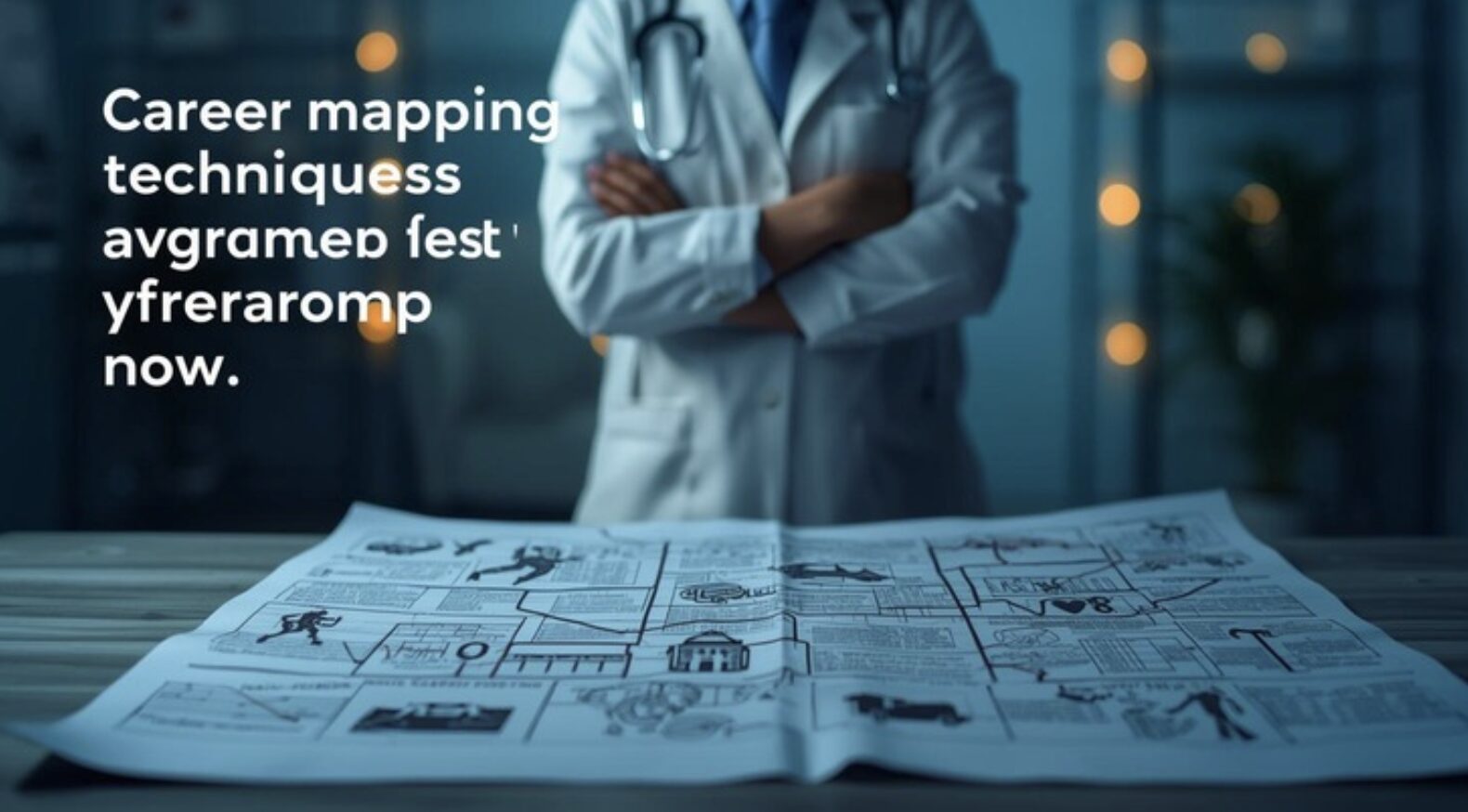


コメント