
もんきち
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、方向性の統一について考えたいと思います。

スタッフ
反対する人はほっとけばいいの?

もんきち
今回は、反対する側の立場に立って考えてみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
新しい業務フロー、評価制度、デジタルツール…。いくら“正しい”仕組みであっても、現場では予期せぬ反発を招くことがあります。特に40人規模のスタッフが在籍するリハビリテーション部門では、管理職の伝え方・巻き込み方が成否を大きく左右します。本記事では、「新しい仕組みを“拒否する側”の視点」に立ち、管理職がとるべき対応を、学術的根拠と実践例を交えて解説します。
なぜ“拒否”が起こるのか ― 現場の声と心理的要因
- 拒否の正体は「反抗」ではなく「不安」
「急に変えるなんて無理」「前のやり方のほうが慣れている」…これは、変化への不安や自己効力感の低下が原因であることが多いです(Bandura, 1997)。
特に、長年同じ方法で働いてきたベテランスタッフほど、新しい方法に対して「自分にはできないかも」という恐れを抱きやすい傾向にあります。 - 組織内“沈黙の壁”も要因
拒否感が強くても、表面化せず、陰で愚痴や不満が広がる「サイレントレジスタンス(沈黙による抵抗)」も問題です(Morrison & Milliken, 2000)。
新制度に対する抵抗のメカニズム ― 学術的背景と理論
- 「変化の段階モデル」:Lewin(1951)の理論
変化には、①解凍(unfreeze)→②変化(change)→③再凍結(refreeze)のプロセスが必要です。
リーダーは、まず「なぜ変えるのか」の納得感を与える段階を踏まずに進めてしまうと、②の段階で抵抗が起こります。 - 心理的安全性が低いと変化は拒まれる
Edmondson(1999)は、チームにおける「心理的安全性」が高いほど、変化やフィードバックを受け入れやすいと指摘しています。
現場が「言っても無駄」「否定される」と感じていれば、どれほど正しい新制度でも浸透しません。
受け入れを促す管理職の対応策 ― 信頼と共感をベースにした浸透戦略
- スモールスタートで“成功体験”を演出する
一斉導入ではなく、一部チームで先行実施し、成功例を共有することで、「これなら自分たちもできそう」と感じさせることが有効です。 - 拒否の声を“否定しない”対話の場をつくる
反対意見を封じると、より強い拒否につながります。意見を傾聴し、「なぜそのように感じるのか」を丁寧に拾い上げる場を設けることが重要です。
例:全体ミーティングとは別に、少人数での“意見交換カフェ”を企画。 - 「仕組み」より「価値」の共有
やり方の押し付けではなく、「この新制度は、患者の満足度やチームの働きやすさにつながる」という価値にフォーカスすることで、共感が生まれます。
まとめ
変化を拒否する現場には、必ず理由があります。リハビリ部門という専門性の高い環境では、管理職は単なる制度の“案内人”ではなく、“共に進む伴走者”であることが求められます。「拒否する声」こそ、現場のリアルな反応であり、改善のヒントでもあります。その声を拾い、信頼と共感を軸にした浸透戦略をとることが、結果的に組織の底力を育てるのです。
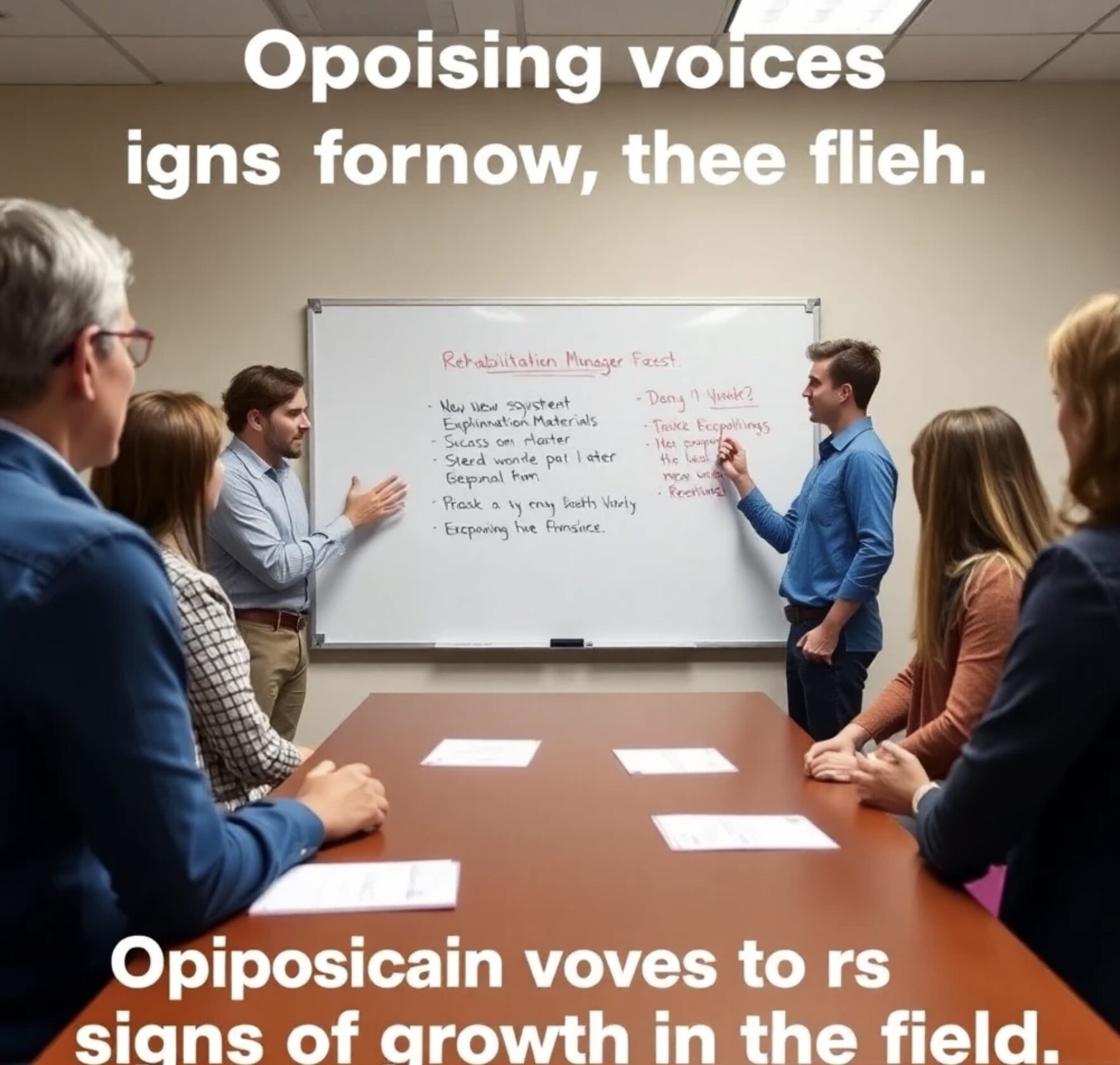


コメント