
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、能動的に動くことについて考えたいと思います。

自分では動いてるつもりですが・・・

今回は、管理者側の心理も含めて考えてみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
リハビリ現場で働く管理職の皆さん。
「なかなか自分から動く人が少ない…」「指示待ちになってしまう…」そんな悩みを抱えていませんか?
特に医療や介護のような専門性が高く、多職種連携が求められる職場では、「前例踏襲」や「ルール重視」が根付きやすく、管理職であっても受け身の姿勢になりがちです。
しかしこれからの時代に求められるのは、「自ら考え、動けるリーダー」です。
では、どうすれば“能動的に動ける管理職”を育て、組織全体を前向きに変えていけるのでしょうか?
この記事では、行動科学や教育心理学の知見をベースに、**管理職が自発的に動き出すための“7つのポイント”**と、実際の現場での導入事例を交えながら、具体的な仕組みづくりのヒントをご紹介します。
なぜ管理職が“受け身”になりがちなのか?
責任の重さが“動きを止める”
管理職は意思決定権を持つ立場である反面、組織の制約や失敗への恐れから、動きが慎重になりやすいものです。特に医療やリハビリ現場では、ミスが患者の安全に直結するため、「前例通り」が優先されがちです。
「正解を求めすぎる」心理
行動経済学者のバリー・シュワルツ(2004)は、選択肢が多すぎたり失敗を恐れる環境下では、意思決定が止まる“決定麻痺(decision paralysis)”に陥ると指摘します。まさに多忙なリハビリ管理職が抱える状況です。
“能動的に動ける”管理職に共通する7つの条件とは?
以下は、教育心理学や行動科学の知見に基づき、「人が自発的に動ける」要素として研究的に裏付けのあるポイントです。
①目的が明確
デシとライアンの「自己決定理論(Self-Determination Theory)」によれば、人は内発的動機づけがあるとき、最も能動的に行動します。目的が自分にとって意味あるものであるかがカギ。
②手段が明確
具体的な行動方法が見えると、取りかかりやすくなります。「何をすればいいか分かる」状態をつくることが出発点です。
③自分で決められる
選択肢があることで「自律性」が生まれます。トップダウンで指示されるより、自ら選んで動けるほうが、責任感とやる気が高まります。
④小さな成功体験で自信を得る
バンデューラの「自己効力感理論」によると、人は小さな成功経験を重ねることで「自分にもできる」という自信を形成します。
⑤適度な難度
簡単すぎても、難しすぎてもやる気は起きません。ちょっとだけ背伸びすれば達成できる課題(ゾーン・オブ・プロキシマル発達)を設定するのが効果的です。
⑥正当な評価と報酬
努力が認められ、対価や賞賛が与えられる環境では、行動の持続性が高まります。組織的な表彰制度やフィードバックの仕組みが効果的です。
仕組みで能動性を引き出す!現場でできる取り組み事例と注意点
実践例1:1on1ミーティングで目的と役割をすり合わせる
月1回、個別面談を通じて「管理職としてどうありたいか」「チームにどんな影響を与えたいか」を言語化することで、自発性を引き出します。
実践例2:チャレンジシートの導入
スタッフ自身が「やりたい改善案」や「挑戦したい業務」に記入できる仕組み。小さな提案が積み上がり、行動につながります。
実践例3:業務改善コンテスト
年1回の全体発表会で、改善提案を共有する文化を育成。評価・表彰をセットにすることで「報酬」と「承認」を両立させます。
注意点:仕組みだけで変わらないこともある
制度やツールが導入されても、現場が「自分ごと」として受け止めていなければ、形式だけが残る結果になります。心理的安全性と信頼関係が前提であることを忘れないようにしましょう。
まとめ
管理職が能動的に動けるようになるには、「やる気」や「根性」だけでなく、心理学や行動科学に基づく仕掛けが必要です。
目的・手段・自由度・成功体験・難易度・評価、この7つのポイントを押さえた職場づくりが、結果としてチーム全体の活性化にもつながります。
「自分で決めて動ける」管理職を育てることは、現場の未来を変える第一歩です。
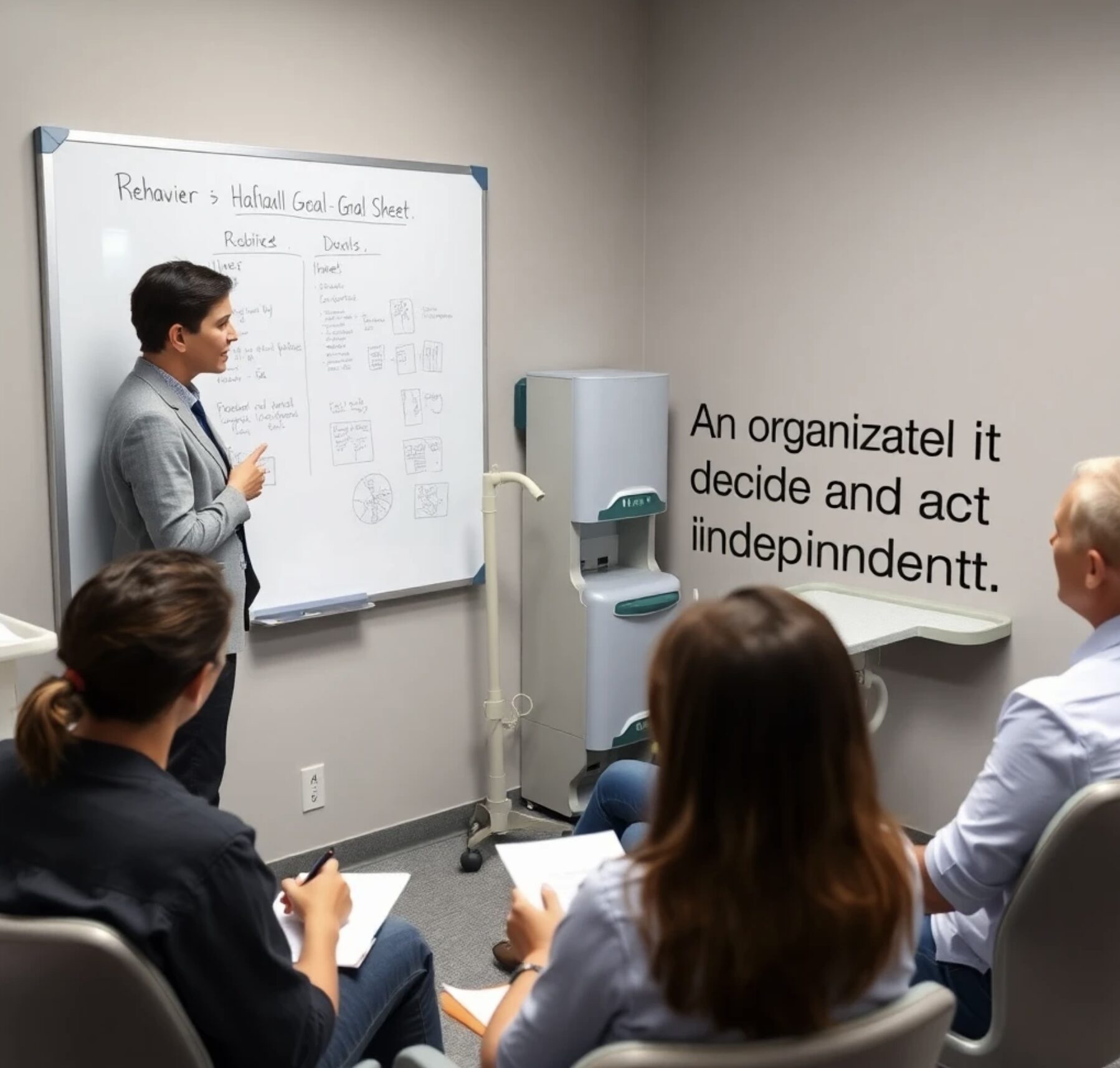


コメント