
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、老害予防について考えたいと思います。

どうすればいいんでしょう?

今回は、老害を防ぐための自問自答について考えてみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
「そんなつもりはなかったのに…」
部下との関係性がすれ違うとき、そう感じる管理職は少なくありません。
リハビリ現場では、世代を超えた連携が欠かせません。
しかし、知らず知らずのうちに、あなたの言動が若手のやる気をそいでしまっているとしたら?
この記事では、「自分は老害になっていないか?」と振り返るための問いかけと、それを日常の習慣として活かす方法をご紹介します。
リハビリ管理職と“老害”の境界線とは?
「老害」とは、年齢や立場を盾に自らの考えを一方的に押しつけ、周囲の成長や環境の変化を妨げる存在を指す言葉です。
本来、豊富な経験や知識を持つ管理職が、意図せずそのように見られてしまう背景には、**“善意の押しつけ”や“変化への抵抗”**が存在します。
たとえば、「私の若い頃は…」という常套句や、「こうするべきだ」といった断定的な言動が、部下にとってはプレッシャーとなり、成長機会を奪っている場合もあります。
学術的には、心理学者アービング・ジャニスが提唱した「集団思考(Groupthink)」の概念が当てはまります。
これは、集団内で異論を言いにくい雰囲気ができることで、健全な意見交換が阻害される状態を指します。管理職の言動次第で、職場の“空気”が大きく変わってしまうのです。
老害化していないか?気づきを促す7つの問いかけ
以下のような問いかけを、自分自身にしてみてください。どれか一つでも「ドキッ」としたら、立ち止まる価値があります。
①「その発言、部下の成長機会を奪っていないか?」
→ 決めつける前に、部下の考えや提案を聞く余地を持つ。
②「“昔はこうだった”という言葉を、週に何回使ったか?」
→ 過去の成功体験の共有は有効だが、頻度や使い方には注意が必要。
③「最後に“ありがとう”と伝えたのはいつか?」
→ 感謝を伝えないリーダーは、距離感を生みやすい。
④「今の若手がどんな価値観を持っているか、知ろうとしているか?」
→ 無関心は、関心を持ってもらえない原因に。
⑤「新しいアイデアに“それは無理だ”と言っていないか?」
→ 否定よりも、“どうすれば実現できるか”の視点を。
⑥「部下の前で、自分の失敗を語れるか?」
→ 自己開示が、安心安全な職場づくりの第一歩。
⑦「自分が話す時間と、部下が話す時間の比率は?」
→ 7:3以上で自分が話しているなら、話しすぎの可能性あり。
これらの問いかけは、組織心理学やコーチング理論でも“自己認知力”を高める方法として推奨されています(Goleman, 1995)。
問いかけを習慣にするための工夫と職場全体への展開
一時的な気づきだけでは、行動は変わりません。問いかけを“習慣”に落とし込む工夫が必要です。
●日誌・ログの活用
「今日の会話で、自分の発言はどうだったか」を振り返る日誌を導入すると、内省の定着につながります。
●1on1ミーティングでの双方向フィードバック
「部下からのフィードバックをもらう時間」を作ることで、管理職自身の“見えない言動”に気づくことができます。
●問いかけを可視化して共有する
会議室やスタッフルームに「問いかけリスト」を貼り出すことで、チーム全体が意識できるようになります。
●若手リーダー候補と一緒に振り返る
未来のリーダーと共に「良い関わり方」を模索するプロセスが、職場に学習する文化を根付かせます。
まとめ
管理職が「老害」と呼ばれるのは、意図的ではなく、無自覚な言動の積み重ねによるものです。
だからこそ、「自分は大丈夫か?」と定期的に問いかけることが、信頼されるリーダーで居続ける鍵となります。
問いかけは、気づきを生み、行動を変え、職場の空気を変えていく力を持っています。
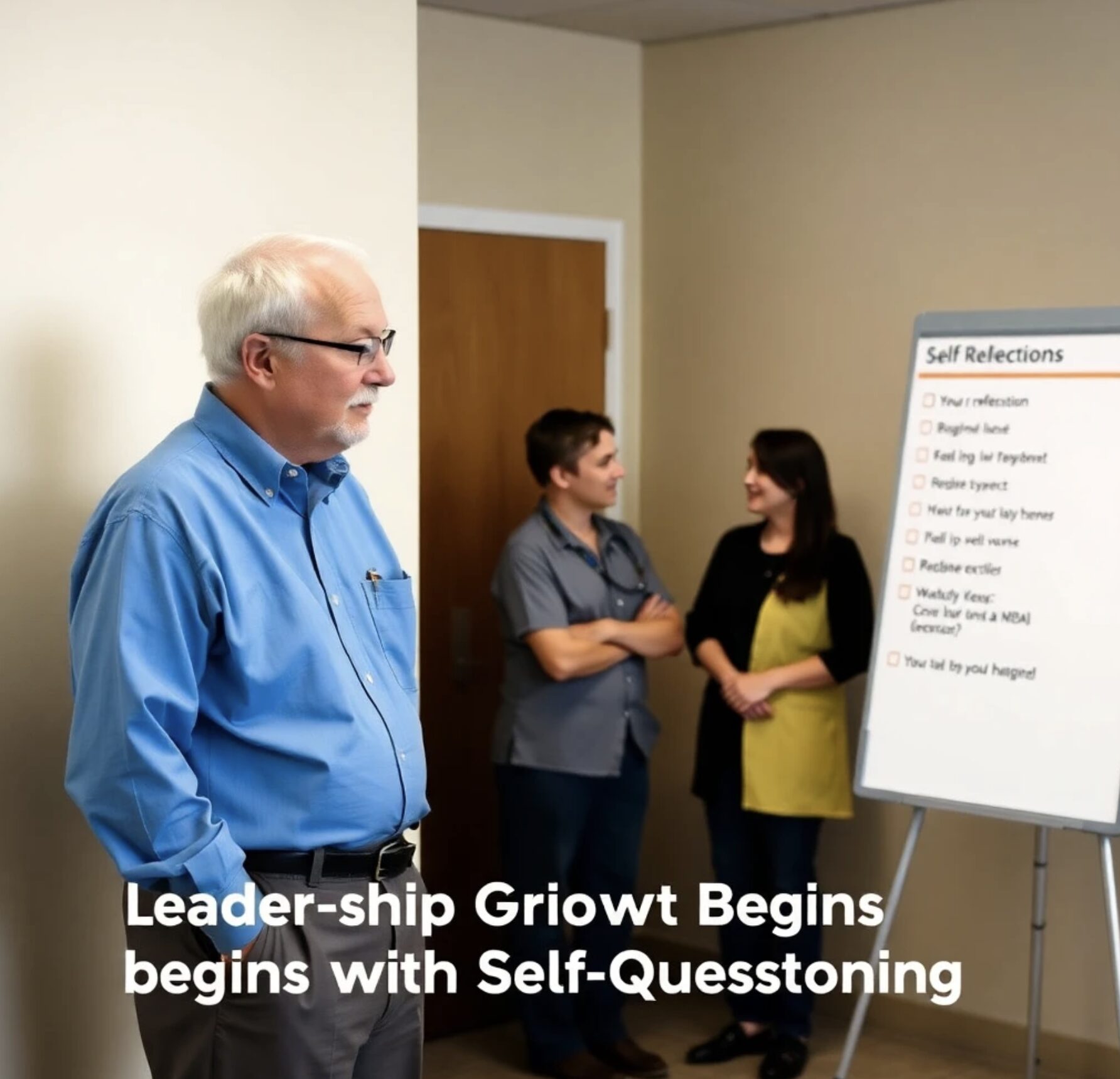


コメント