
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、女性ならではの悩みについて考えたいと思います。

女性にしかわからない?

今回は、女性管理職が取り組んでいる一例を見てみましょう!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
「管理職になっても、悩みを相談できる場所がない」――
リハビリの現場で、そう語る女性職員の声は少なくありません。
特に育児や更年期といったセンシティブな話題は、同僚にも相談しづらく、一人で抱え込む傾向が強まります。
本記事では、リハビリ現場における“女性同士の悩み共有の場”の設置による実践的な変化と、制度設計のヒントを探ります。
女性管理職が直面する“二重負担”とは?
リハビリ現場における女性管理職の登用が進む一方で、「辞めたくなる」理由として多く挙がるのが“二重負担”です。育児、家事、更年期による体調の波など、ライフイベントと職務の両立は容易ではありません。
とくにリハビリ職場では、早朝からの患者対応や多職種調整といった時間的拘束、対人ストレスの高い業務が日常化しています。
厚生労働省の「働く女性の健康課題に関する調査」によると、更年期の症状によって仕事のパフォーマンスが低下したと答えた女性は全体の約50%を占めており、そのうち30%以上が「職場に相談できる人がいない」と回答しています。
“悩みを共有する場”が職場を変える
そんな中で注目されているのが、「悩みを共有できる場」の設置です。
例えば、ある地域のリハビリ病院では、女性管理職主導で月1回の「更年期×子育て共有会」を開催。匿名投稿もできる意見ボックスや、リーダー職による聞き取り制度も並行して導入したことで、参加率は平均75%を超えています。
心理的安全性が高まることで、「人間関係の悩みを吐き出せる」「もう一人で抱え込まなくていい」といった声が続出。離職率は前年から25%減少し、仕事へのエンゲージメントも上昇したと報告されています。
厚生労働省の職場支援調査でも、「相談機会のある職場は離職リスクが低い」とのデータがあり、共有の場の効果は実証的裏付けがあるといえるでしょう。
リハビリ職場ができる“柔軟制度”の設計
単に場を設けるだけではなく、それを制度として支える仕組みも重要です。
リハビリ職場で今後取り入れるべき制度としては、以下の3点が挙げられます:
- 育児短時間勤務者の管理職登用モデルの導入
柔軟勤務でも評価される制度があることで、若手女性のキャリア志向が高まります。 - 産業医や心理士との連携による更年期支援
「更年期のセルフチェックシート」や医療相談窓口の設置で、早期対応を促進。 - ピアサポートネットワークの整備
管理職同士の「悩みの言語化」が進むことで、孤立を防ぎ、継続的な改善文化が育ちます。
このような取り組みは、ジョブ・クラフティング理論(仕事に意味づけし、自己調整する力)にも通じる柔軟なマネジメントです。
まとめ
リハビリ現場における女性管理職の持続的活躍には、業務だけでなく「感情や身体の声を共有できる環境」づくりが欠かせません。
“お悩み共有の場”は、単なる雑談会ではなく、心理的安全性と組織の活力を高める基盤です。
育児や更年期というライフステージを経る中で、制度と心の両面から支える取り組みは、今後の女性活躍推進において重要な要素となるでしょう。
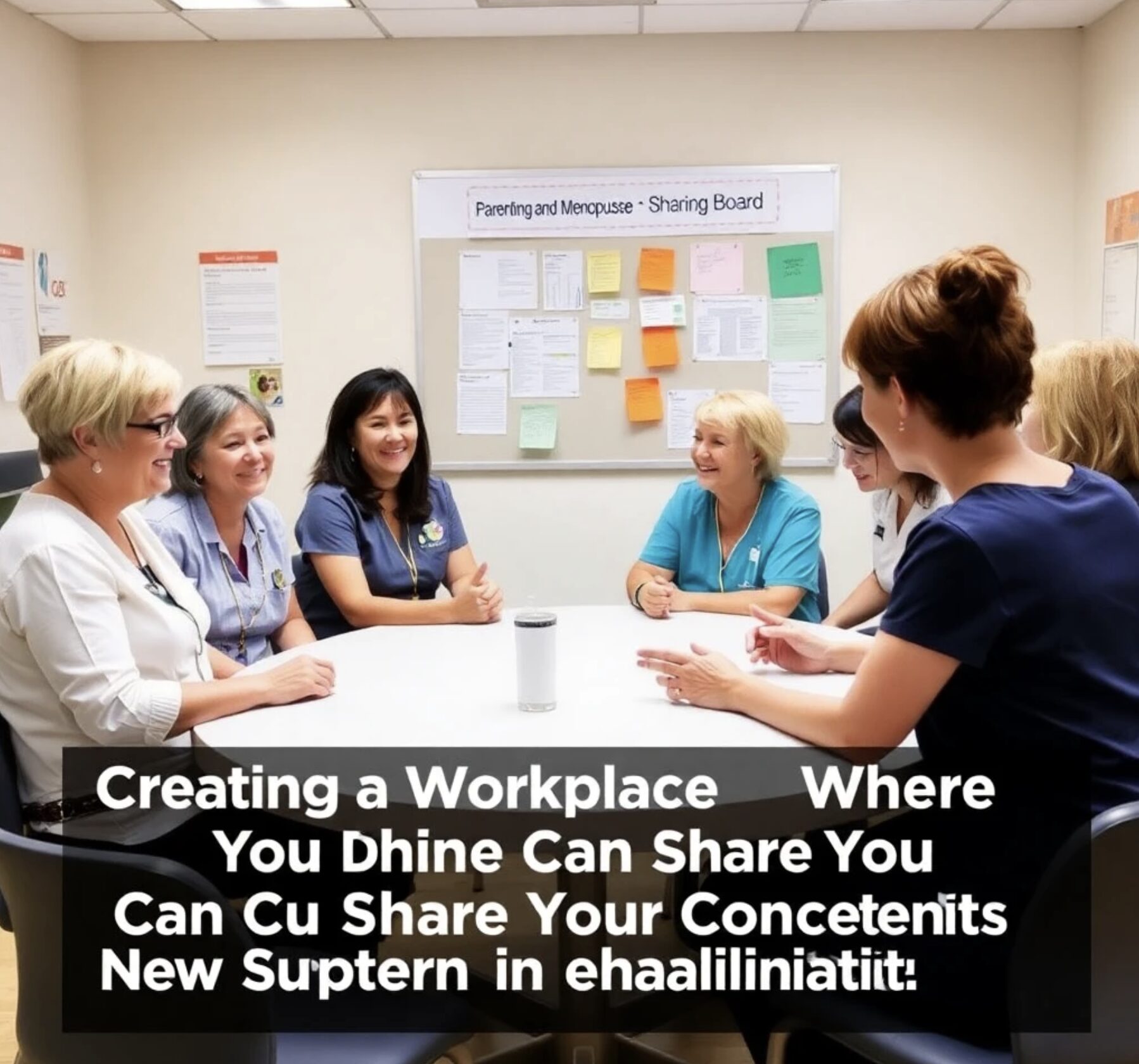


コメント