
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、経験の伝え方について考えたいと思います。

どうすればいいんでしょう?

今回は、老害化を防ぐためにも、経験を上手に伝えることは重要ですね!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
リハビリの現場で長年の経験を積み、管理職としてのポジションに就いたものの――
「若手と距離を感じる」「意見が通らない」「ベテラン扱いされているだけで、本当の信頼がない気がする」。
そんな“違和感”を覚えていませんか?
近年、医療・リハビリの現場では、年齢や経験よりも共感力・対話力・柔軟な姿勢が評価される傾向が強まっています。ベテラン世代が無意識のうちに「老害」と見なされ、若手との信頼関係が築けないケースも少なくありません。
本記事では、「経験だけでは伝わらない時代」に管理職が“老害化”を防ぎ、若手スタッフと建設的に協働するためのポイントを、学術的な根拠とともに具体的に紹介します。
世代を超えて信頼されるリーダーを目指すあなたに、ぜひ読んでいただきたい内容です。
経験だけでは通じない時代背景と若手の視点
かつては「経験こそが信頼の証」でした。しかし、現代のリハビリ職場では、必ずしも経験年数が信頼に直結するとは限りません。
特にZ世代以降の若手スタッフは、「成果の共有」「成長機会の公平性」「対話による納得」を重視します。上下関係ではなく、共感と相互理解によるリーダー像が求められているのです。
厚生労働省が提示する「ハラスメント対策マニュアル」でも、上司の価値観の押し付けや、不適切な指導が離職や職場不信を招くことが明記されています。
時代の変化に応じたマネジメントの柔軟性が、今こそ必要とされています。
「老害」と思われないための自己チェックポイント
知らず知らずのうちに、「老害」と思われてしまう管理職には、いくつかの共通点があります。以下のような行動を、日常で取っていないか振り返ってみましょう。
- 「とりあえず昔のやり方でやってみて」と若手の提案を退けていないか?
- ITやSNS、オンライン会議ツールに距離を置いていないか?
- 指導のつもりで「おれの頃はな…」と話していないか?
このような振る舞いは、若手にとって「壁」や「疎外感」となりやすく、モチベーションの低下や早期離職の原因になります。
若手と協働するために管理職が実践すべき行動
では、どうすれば若手と良好に協働し、老害化を防げるのでしょうか。
ここでは実際に現場で有効だった3つの実践行動を紹介します。
- チーム形成の心理プロセスを理解する(タックマンモデル)
チームは「形成→混乱→統一→成果」という段階を経ることが知られています。リーダーがこの過程を理解し、混乱期に感情的にならず支えることで、信頼関係が築かれます。 - 経験は「引き出されて語る」形で伝える
若手が困っている時に「助言」として伝えることで、経験が「押しつけ」ではなく「価値ある知見」に変わります。 - 心理的安全性を確保する1on1の実施
Googleの研究でも注目された「心理的安全性」は、若手が安心して意見を言える関係を意味します。月1回でも1on1の時間を持ち、双方向の対話を行うことが重要です。
まとめ
リハビリ現場における管理職は、「経験豊富=正解」ではなく、「経験をどう伝えるか」「どう協働するか」が問われる時代に突入しました。
若手との摩擦を避け、老害と見なされずにリーダーシップを発揮するには、柔軟性・共感力・対話姿勢が不可欠です。
本記事で紹介した3つの実践ポイントは、どれも今日から取り組めるものばかり。
世代を超えてチームを育てる――そんなリーダー像を目指して、一歩を踏み出してみませんか?
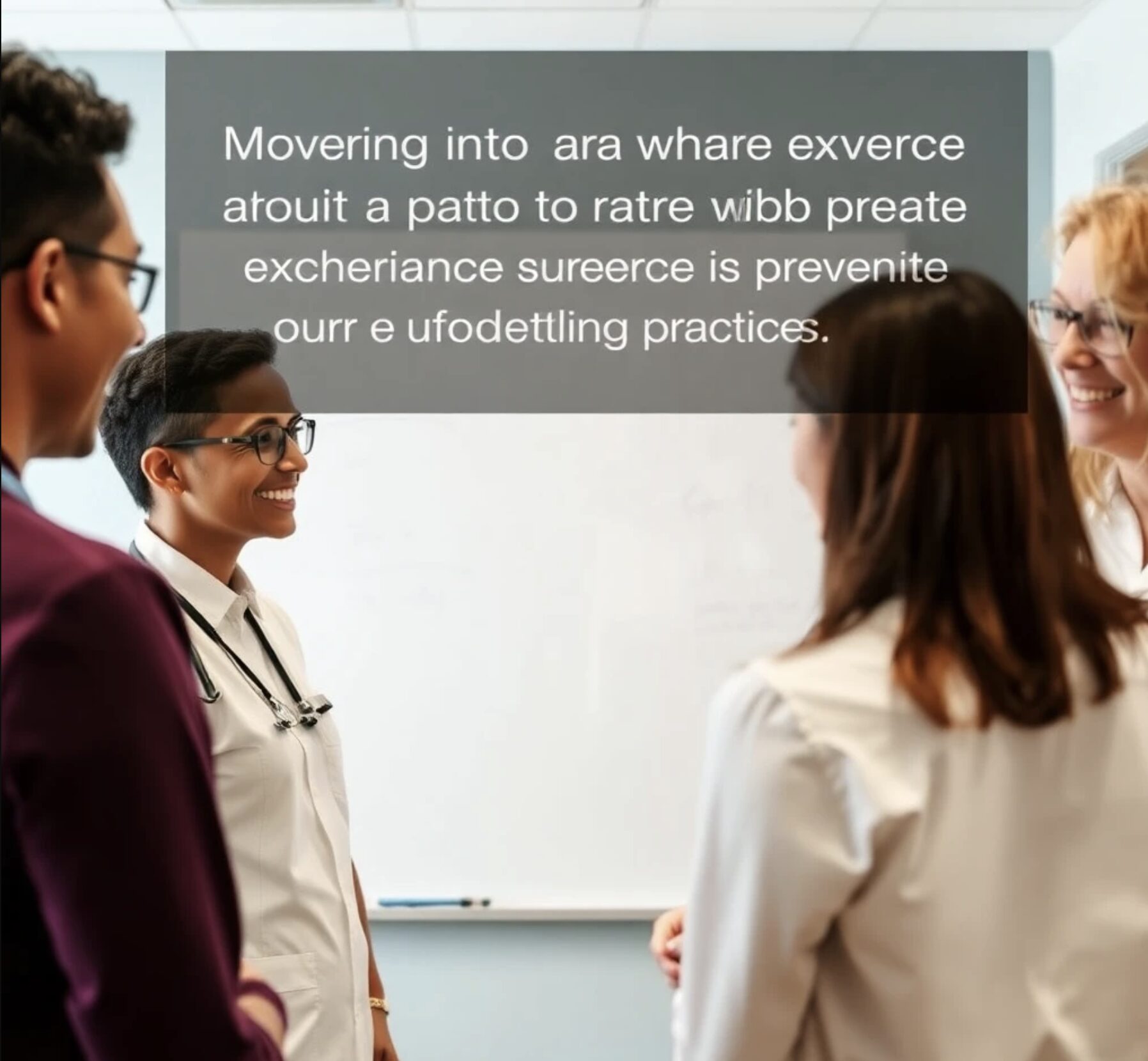


コメント