
みなさん、こんにちは!もんきちです。
今回は、グローバル人材について考えたいと思います。

世界に目をむける必要あるの?

現場の今だけをみてるだけでは、時代の波に乗り遅れます!
こんな方にオススメ!
- マネジメント初心者の方!
- 医療管理職の方
はじめに
グローバル人材育成――これは、もはや遠い世界の話ではありません。特にリハビリテーション専門職の管理者にとって、国際的な視点を持つことは「現場改善」や「人材定着」「多職種連携の質向上」に直結する重要な鍵となっています。
ではなぜ今、グローバル人材育成が注目されているのでしょうか? 本記事では、WHOやOECDの国際的な潮流を踏まえながら、リハ職管理者が取り組むべき具体的アクションを、事例とともに解説します。
なぜ今、グローバル人材育成がリハ職管理者に必要なのか?
近年、WHOやOECDといった国際機関が「医療従事者のグローバル対応力」を急速に重視し始めています。特に、パンデミックや災害時対応、そして国際協力・保健支援の現場で、多文化対応力・チームマネジメント力・デジタル活用能力が求められています。
背景となるデータ
- **WHOの「Global Strategy on Human Resources for Health(2030)」**では、リハビリ人材の国際的育成を重点分野と定義
- **OECD Health at a Glance(2023)**によれば、医療ICT活用率と多文化対応研修の有無がリーダーの職務満足度と関連
なぜ「管理者」が鍵となるのか?
現場の教育を変える主体は、日々の業務運営を担う中間管理職です。彼らがグローバル思考を持ち、現場に展開できなければ、どれほど上位方針が整っても“現場浸透”は難しいのが現実です。
グローバル人材育成の潮流と、リハ管理職に求められる3つの変化
WHO‐EMROやOECDレポートに共通して示されるのが、**「国際的視座でのリーダー育成」**というキーワード。そこには以下の3つのシフトが含まれています。
組織内「縦」から、職種間「横」へ
リーダーは自職種内だけでなく、看護師・MSW・経営層との協働を推進するファシリテーターへ。
医療の“外”とつながる意識
NGO、地域行政、IT企業など、医療外リソースとの連携を主導する役割へ。
現場の成功体験を「再現可能なモデル」に変える力
優れた取り組みを「モデル化」「マニュアル化」し、他部署・他施設へ展開できるスキルが問われる。
重要な示唆:
単なる現場力ではなく、**“汎用性ある思考と再現可能な実践”**を担う管理職が、国際的な人材と評価されます。
リハ職管理職が今すぐ始められる、グローバル人材育成アクション3選
変化は一歩ずつ。現場に即した具体的なアクションから始めることが、未来のリーダーへの第一歩です。
アクション1:国際指標を使った自己評価
- WHOが提示する「リーダー育成の評価指標(LEAD tool)」を用いて、自部署の教育・意思決定スタイルを見直す
- KPI:毎年1回、部署マネジメントの評価項目を国際水準と比較
LEADツール簡易チェックリスト(日本語版)
目的:
自身または部下のリーダーシップスキルを可視化し、成長課題を明確にするために使用します。
各項目を「1=まったく当てはまらない」〜「5=非常によく当てはまる」で評価してください。
① 戦略的思考・ビジョン設定
| 項目 | 評価(1〜5) |
|---|---|
| 長期的な目標やビジョンを明確に描き、部下と共有している | |
| 組織やチームのミッションと整合性のある行動ができている | |
| 社会的・医療的変化(制度・人口動態等)を意識した判断を行っている |
② コミュニケーションと対人関係
| 項目 | 評価(1〜5) |
|---|---|
| 部下や同僚の意見に耳を傾け、対話を重視している | |
| 困難な状況でも感情的にならず、冷静な対話ができる | |
| 伝えるべきことを分かりやすく、タイミング良く伝えている |
③ チームマネジメントと育成力
| 項目 | 評価(1〜5) |
|---|---|
| メンバーそれぞれの強みを理解し、役割を最適に配置している | |
| 後進の成長を促すフィードバックや指導を行っている | |
| チームのモチベーションと成果を同時に引き出せている |
④ 意思決定と責任
| 項目 | 評価(1〜5) |
|---|---|
| 情報を分析し、根拠ある判断を行っている | |
| 組織の方針やルールを尊重したうえで決断を下している | |
| 自身の判断に対して責任を持ち、説明責任を果たしている |
⑤ 自己認識と自己改善
| 項目 | 評価(1〜5) |
|---|---|
| 自身の強み・弱みを正しく理解し、行動を調整している | |
| フィードバックを素直に受け止め、成長の糧にしている | |
| 専門職としての成長意欲が継続的にあり、学習を続けている |
評価の活用方法
- 合計点/各項目の平均点を出すことで、強み・課題を把握できます。
- 年に1~2回の定期チェック+上司・部下・同僚による360度評価を組み合わせるとより効果的。
- 評価後には、【今後のアクションプラン】(例:半年間で強化したい項目など)を立てることが重要です。
アクション2:越境的な対話の機会を設ける
- 多職種混成ワークショップや「チーム対話型症例検討会」を開催
- KPI:年間3回以上、多職種や他法人と連携した“共創型学習”の実施
アクション3:スタッフと共に「国際的マインド」を育てる
- 例えば「SDGs × 医療」をテーマにした勉強会などを実施
- KPI:年1回、リハビリ部門として「国際的課題」を共有する場を設ける
以上を通じて、グローバル人材とは「英語が話せる人」ではなく、**“異なる視点を受け入れ、再構成して行動できる人”**であると再定義されます。
まとめ
ローバル人材育成というと、語学力や留学経験といったイメージが先行しがちですが、実際に今求められているのは、**“多様な価値観や視座を受け入れ、それを自職場の文脈に翻訳できる力”**です。
管理者であるあなたが一歩を踏み出せば、組織の文化そのものが変わります。国際的な知見を現場で生かすことは、「患者のQOLを高める」ことにも直結します。
ぜひ、あなたの職場から“次の未来型リーダー”を育てる意識を、今日から始めてみませんか?
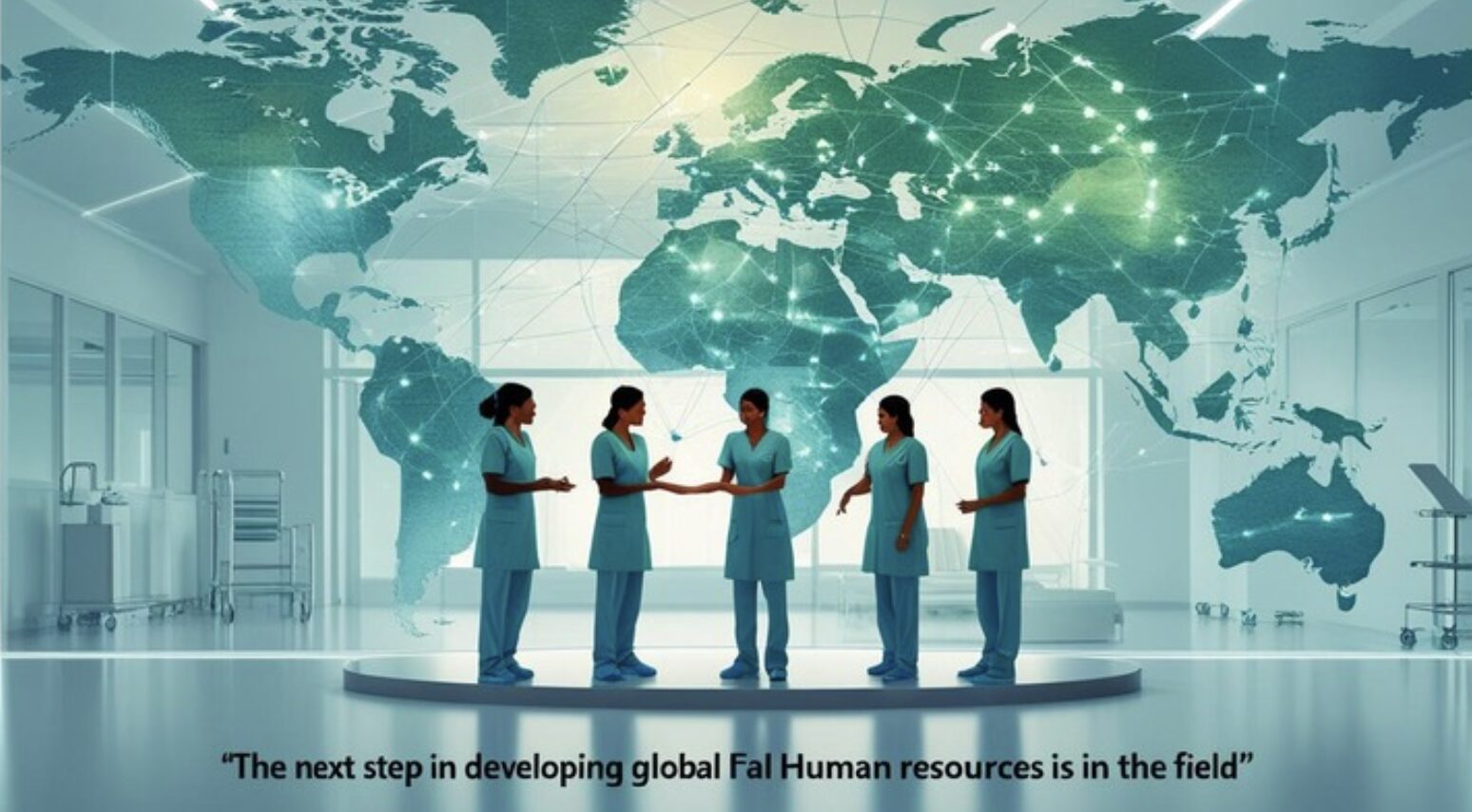


コメント